実を言うと、わたし自身は中学・高校時代に「過去問」を購入して解いたことが一度もありません。
何故なら、受験に本気で向き合っていなかったため、「過去問」が市販されていたかも知らなかったからです。
ところが、実際に中学受験が終わってみると驚きました。
塾には過去問の進捗状況を記録した一覧表が掲示されていましたが、その表で着実に演習を進めていた子どもたちこそが、都立中高一貫校に合格していたからです。
過去問演習は「いつから」「どれくらい」やるべきか?
結論から言うと、子どもが通っていた塾では、6年生の11月中旬から各都立中高一貫校の「適性Ⅱ・適性Ⅲ」を 過去5年×3周分をやり切るように指導されていました。
- 適性Ⅱ: 11校 × 5年分 ≒ 55回
- 適性Ⅲ: 7校 × 5年分 ≒ 35回
合計でおよそ90回分になります。
1回45分だとすると、4,050分(約68時間)を演習に充てる計算になります。
もっとも、適性Ⅱは複数校で共通問題が出されるため実際の回数は少し減ります。
ただし、復習や解き直しを含めると、最終的にはこの倍近い時間が必要になると思います。
なお、わが家の場合、過去問に取り組む際は常に時間を計りましたが、制限時間を設けることはしませんでした。
というのも、初めて見る問題にじっくり思考すること自体が大事だと考えたからです。
実際、小石川中等教育学校の問題を最初に解いたときには、制限時間45分のところ100分もかかってしまいました。
なお、都立中高一貫校の過去問へのリンクをまとめた記事がこちら。
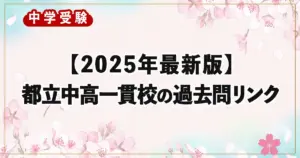
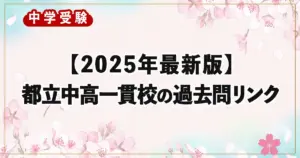
過去問を「得点源」に変える2つのポイント
過去問をただ解くだけで終わらせてしまうだけでは、なかなか点数に結びつかないと思います。
そうならない為にも、わたしが塾の先生から受けたアドバイスも交えながら、効果的な過去問の取り組み方を紹介します。
本番を想定した環境づくり
過去問を解く際には、可能な限り入試本番に近い環境を再現することが重要だと思います。
- 環境設定
-
タイマーをセットし、静かで集中できる環境を整えます。そして、問題用紙と解答用紙を本物に近いサイズにコピーし、筆記用具など机の上に置くものも本番と同様にします。
- 時間の使い方
-
過去問を解き始める前に、まず全体をざっと見て、解く順番や各大問にかける時間配分を最初に決める習慣をつけましょう。
過去問に取り組む時間帯は、本番と同様の午前中に取り組むことをオススメします。
また、公立中高一貫校の適性検査では記述問題がメインのため、解答用紙を同一サイズ(A3)にすることはマストだと思います。
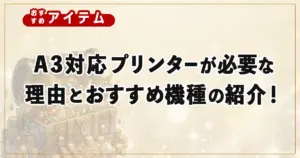
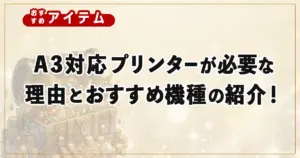
採点と原因分析
過去問演習の成否は、「復習」にかかっていると言っても過言ではないと思います。
まず、自己採点を子どもに任せると甘くなりがちなので、できるだけ保護者が採点をしましょう。
その際、間違えた問題はすぐに答えを見せず、ヒントを与えてもう一度考えさせるのが理想です。
そうすることで、子どもがその単元を理解しているのか、それとも全く歯が立たないのかを見極めることができます。
一口に「不正解」といっても、正解に至るまでの過程には段階があります。
知識不足によるものなのか、問題文の読み違えなのか、あるいは単なるケアレスミスなのか、その違いを把握しておくことで、弱点補強だけでなく、中学受験本番に向けた志望校選びの参考にもなるはずです。
もちろん、1か月ほど時間を空けたら「解き直し」をすることも忘れないでください。
再度取り組むことで、理解しているかどうかを確認できるほか、繰り返しによって記憶が定着するので、学習効果が格段に高まっていくと思います。
まとめ
下記のような理由で過去問に手をつけないのは、おそらく間違いです。
- 3割しか取れないそうにないから
- 子どもが自信をなくしてしまうからもう少し完璧にしてから
- 試験範囲の勉強がまだ終わってないから
過去問は単なる問題集ではなく、志望校が子どもに投げかける“メッセージ”でもあると思います。
だからこそ繰り返し解くことで、その学校の出題傾向に合わせた知識が自然と身につきます。
過去問を通じて弱点をあぶり出し、志望校の求める力に近づいていく──。
このサイクルを重ねることで、点数だけでなく精神面でも「やるべきことはやった」と胸を張れるようになると思います。
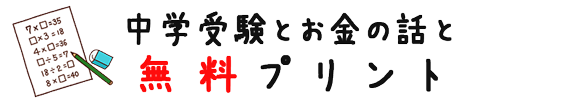
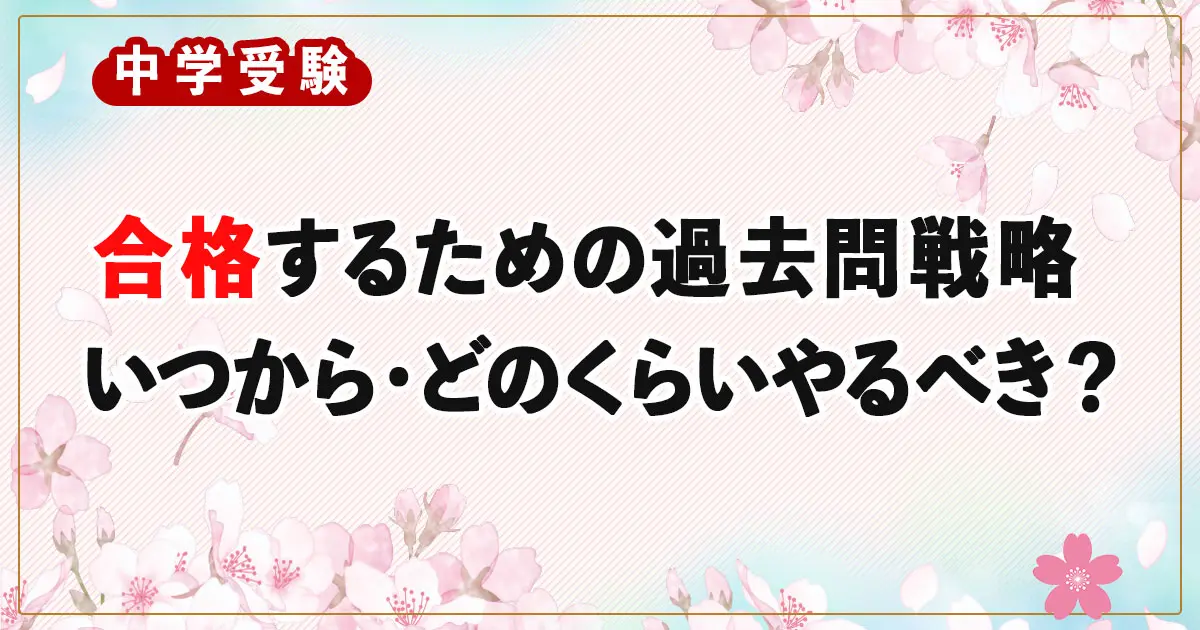

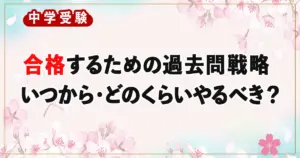
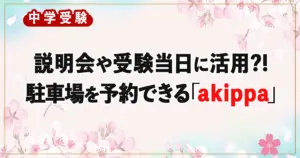
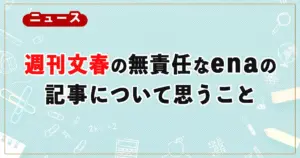
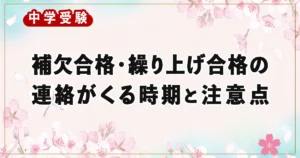
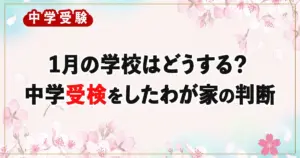
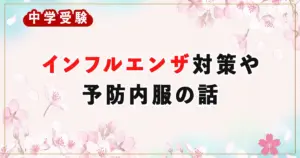
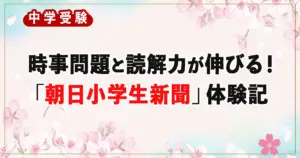
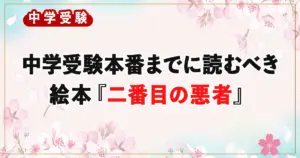
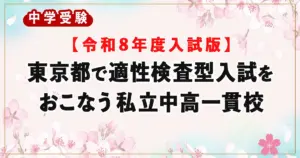
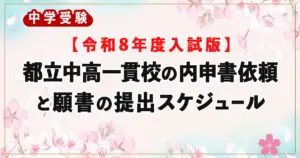
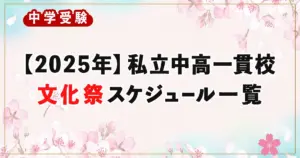
コメント