わが家の子どもは、運動や勉強、音楽など「苦手ではないけれど得意でもない」タイプ。
そのためか、
学校つまらないな・・・。
とつぶやくこともしばしば──。そんな状態だったので、成績も特に目立つものではありませんでした。
ところが、小学4年生になったある日を境に大きな変化が訪れます。
それが「Scratch(スクラッチ)」との出会いです。
学校の授業で初めて触れたこの「Scratch(スクラッチ)」が、わが子のやる気スイッチを一気にONにしてくれました。
「Scratchで科学実験」は、自由研究の課題としても使えるのでオススメです。


Scratch(スクラッチ)とは?
Scratch(スクラッチ)は、マウス操作だけでプログラムを組むことができる、無料のビジュアルプログラミング言語です。
日本語にも対応しており、たとえば「10歩動かす」「1秒待つ」などの命令ブロックをドラッグ&ドロップでつなげることで、キャラクター(初期設定ではネコ)を自在に動かすことができます。


慣れてくると、アクションゲームやクイズ、アニメーションなどを自由に創作できます。
友だちと一緒にゲームを作るように・・・
学校の休み時間では、絵が得意な子、ゲームが好きな子、そしてプログラミング担当だったわが子と、自然と役割分担が生まれ、Scratchを使ったゲーム制作を友だちと一緒に取り組むようになりました。
「友だちと協力してひとつの作品をつくる」という体験は、わが子にはとても新鮮で、大きなモチベーションになったようです。
そのためか、プログラミング担当のわが子は、自宅でも100個以上のブロックを使ったループ処理を、あれこれ試行錯誤しながら組み立てていました。
そして、完成したシューティングゲームを遊ばせてもらうと──
この弾は、当たっていないように見えるけど、実は当たっちゃうという罠なんだ!
それはクソゲーでは・・・。
という感じでしたが、意欲的に何かに取り組むようになったのはよかったです。
そして、さらに深く学べるようにと、子どもが興味を持ちそうな「Scratchの講座」をUdemyで受講させてみたところ、
玉の動きは三角関数で作るらしいよ!
と話してくれるようになり、算数や数学への関心も自然と高まりました。
ちなみに、Udemyはオンラインで学べるプラットフォームで、日本ではベネッセコーポレーションが運営しています。
そして、次のステップへ──「レゴでプログラミング」体験
さて、Scratchにすっかりハマったわが子が、次に興味を持ったのがレゴ×プログラミングです。
ちょうどその頃、近所に子ども向けのプログラミング教室ができたこともあって、教室の無料体験や、大学で開催されたプログラミング体験イベントにも参加しました。
その時に使った教材が、「LEGO® Education SPIKE™」でした。
これは、Scratchベースのアプリと連携し、レゴブロックをプログラムで自在に動かすことができる教材で、タブレット上で命令ブロックをドラッグ&ドロップするだけの直感的な操作が可能です。


さらに中高生向けには、プログラミング言語「Python(パイソン)」を使った高度な動作制御や、機械学習ライブラリ「TensorFlow(テンソルフロー)」との連携も可能で、STEAM教育の実践教材としても注目されています。
わが家は中学受験を選んだため、プログラミング教室への通学は見送りましたが、レゴは子どもの学ぶ意欲を育てるためにもオススメのおもちゃ(教材)だと思います。
「LEGO® Education SPIKE™」は、レゴの公式オンラインショップで販売されています。
STEAM(スティーム)教育とは、科学・技術・工学・芸術・数学の5分野を横断的に学び、創造力や課題解決力を育む教育のことです。
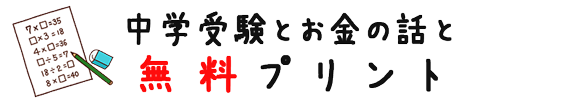



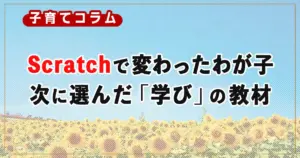
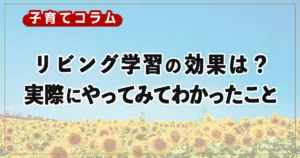
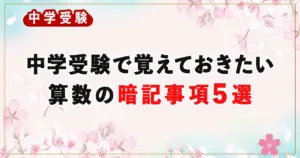
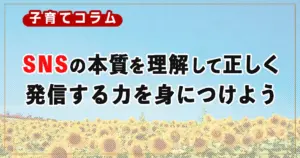
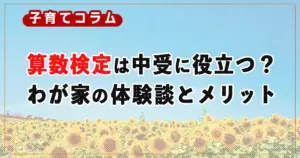
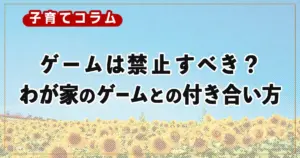
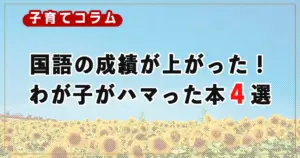
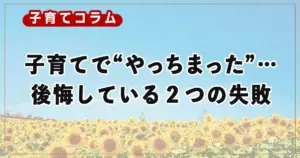
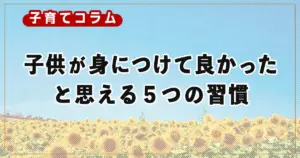
コメント