わが家の進学の選択肢のひとつとして中学受験を考えたとき、さまざまな疑問が浮かびました。
そこで当時感じた疑問を思い返し、Q&A形式でまとめてみました。
なお、回答は私自身の経験や、一般的だと思われるケースをもとにした主観的な内容です。
すべてのご家庭に当てはまるとは限りませんので、その点をご理解いただければ幸いです。
中学受験準備と学習に関する疑問
中学受験準備と学習に関する疑問についてまとめてみました。
\クリックで開閉できるよ!/
Q.中学受験の準備はいつから始めるのが一般的ですか?
私立中学の受験は、一般的に小学3年生の2月頃から始めるのが良いとされています。
何故なら、私立中学の受験範囲は広範囲に渡るため、約3年かけて準備をしないと間に合わないからです。
なお、公立中高一貫校であれば、小学4年生の2月頃からでも間に合うと思います。
Q.塾なしで中学受験は可能ですか?
塾に通わずに中学受験を目指すことは可能です。
ただし、そのためには、保護者の手厚いサポートと、計画的かつ戦略的な家庭学習が欠かせません。
すべてを親だけで対応するのは現実的ではないため、Z会や進研ゼミといった通信教育を活用したり、必要に応じて家庭教師にスポットで依頼したりすることが現実的な選択肢だと思います。
Q.中学受験にかかる費用の目安はどれくらいですか?
中学受験の主な費用としては、塾代(テキスト代含む)、受験料、入学金、そして入学後の学費などが挙げられます。
中学受験対策は、小学4年生から本格的にスタートするのが一般的で、そこからの3年間でかかる塾の費用は平均で約200万円とされています
都立(公立)中高一貫校に関する疑問
都立(公立)中高一貫校に関する疑問についてまとめました。
\クリックで開閉できるよ!/
Q.都立(公立)中高一貫校は複数受検できますか?
都立(公立)中高一貫校の受検は、原則として1校のみに限定されています。
このような厳しい制約があるため、多くの受検生は、都立(公立)中高一貫校と同じ「適性検査」タイプの入試を実施する私立中学を「練習校」として併願することが一般的です 。
Q.公立中高一貫校は県をまたいで受検できますか?
たとえば、都立中高一貫校の受検資格は、原則として東京都内に居住していることが条件となります。
逆に、埼玉県立の中高一貫校は、都内在住者であれば受検できません。
また、合格後も都内から通学することが求められ、入学日までに保護者とともに東京都内に転入していることが必須要件です。
さらに、入学後も継続して東京都内に住み続けることが義務付けられているため、親の仕事の都合などで他県へ転居した場合には、転校手続きをとることになります(※個別事案なので例外もあると思います)。
Q.公立中高一貫校には復学制度があるの?
私立中学校では、親の海外転勤などにより休学・復学を認めている学校が多く見られます。
一方で、公立の中高一貫校にも復学制度が設けられているケースがあります。
すべての学校に制度があるとは限りませんが、近年では留学プログラムも活発におこなわれており、後期課程(高校相当)になると、実際に海外留学を経験する生徒も一定数います。
そのため、復学に関しても比較的柔軟に対応してもらえる学校が多いと言えるでしょう。
私立中学に関する疑問
私立中学に関する疑問についてまとめました。。
\クリックで開閉できるよ!/
Q.私立の寄付金は払わなくてはいけないの?
寄付金は「任意」と書いてある場合が多いですが、それは「口数」のことだと考えましょう。
表面上は任意かもしれませんが、基本はマストです。
なお、少数ですが寄付金自体がない私立もあります。
その他:中学受験に関する疑問
その他の中学受験に関する疑問についてまとめました。
\クリックで開閉できるよ!/
Q.学費を軽減する奨学金制度や補助金はあるの?
学費の負担を軽減するための制度は、学校独自の奨学金から、地方自治体による補助金まで、さまざまな形で用意されています。
国による私立中学校への直接的な支援制度は2021年度で終了しましたが、その影響もあってか、多くの自治体が授業料の一部を補助する助成制度を拡充しています。
なお、これらの制度には申請時期や期限があるため、気になった段階で早めに自治体などの窓口に確認することをおすすめします。
Q.小学校の先生に内申書を書いてもらう際、お礼は必要ですか?
小学校の先生に内申書(調査書)の作成をお願いする際、個人的な金品によるお礼は控えるべきです。
公立学校の教員は、国家公務員倫理法に基づき、職務に関連して利害関係のある相手から贈与を受け取ることが禁止または制限されています。
たとえ少額であっても、先生にとっては「気を使わせる」ことになりかねません。
そのため、お礼は連絡帳などに感謝の言葉を添える程度が、適切で負担にならない方法だと言えると思います。
Q.合格後、小学校や塾の先生にお礼はすべき?
公立学校の教員は、国家公務員倫理法に基づき、職務に関連して利害関係のある相手から贈与を受け取ることが禁止または制限されているので、控えた方がいいと思います。
ただ、塾の先生へのお礼は問題ないと思います。
お礼の品の値段の相場は、2,000円~3,000円程度が目安とされていて、個包装で手軽に消費できるお菓子や飲み物(菓子折り、ゼリー、ドリップコーヒーなど)が一般的だと思います。
わが家では公立中高一貫校の得点開示結果を塾(ena)に報告しに行く際、感謝の気持ちを込めて菓子折りを持参しました。
このFAQページでは、実際に中学受験を経験する中で感じた疑問をまとめています。
あくまで私自身の体験に基づいているため、すべての方に当てはまらない部分もあるかもしれませんが、これから中学受験に臨む方の参考になれば幸いです。
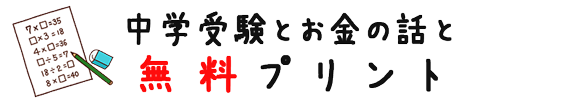

コメント