わたしは以前、大手出版社で幼児〜小学生向けの教材を販売していた経験があります。
その時に上司から繰り返し言われていた言葉が、「勉強は、楽しいからこそ続く」 ということでした。
つまり、子どもの学びは「遊びの一環」として取り組める時にこそ、自然に続けられ、知識も無理なく身に付くというのです
だからこそ、幼児教育では、“遊びながら学べる”教材が人気でした。
そして今回は、その“学ぶ楽しさ”を引き出してくれる 『ドラえもんのおもしろ攻略』シリーズを紹介します。
毎月1冊ずつリビングに増やしていくことが、子どもが継続して読み続けるコツだと思います。
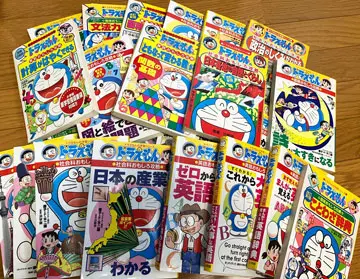
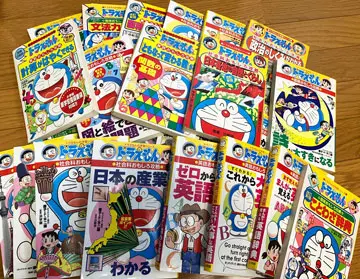
対象:小学1年生~
- 漫画が好き
- 勉強に苦手意識を持って欲しくない
- 色々な事に興味を持って欲しい
難易度・目的
ただの漫画じゃない!塾も監修する本格派
子どもにとって、ドラえもんは教科書よりもずっと身近で親しみやすい存在です。
そのドラえもんが、算数や国語などを漫画で教えてくれることで、子どもは「勉強」という意識を持たずに読むことができます。
まぁ、わが家の子どもは、
のび太のくせに、理解力が高いからなんかむかつく!
と怒ってもいましたが──。
また、このシリーズの魅力は、単元ごとに子どもがつまずきやすい学習の悩みに的を絞っている点にあります。
たとえば、「割り算が苦手」「読書感想文が書けない」といった壁に直面したときでも、ドラえもんの楽しいストーリーとわかりやすいイラストが、視覚的に「なぜそうなるのか」を自然に理解させてくれます。
さらに一部のシリーズは、中学受験で高い実績を持つ浜学園や日能研といった有名学習塾が監修しています。
わが家で効果を実感した5冊
『ドラえもんのおもしろ攻略 』シリーズには、
- ドラえもんの算数おもしろ攻略
- ドラえもんの国語おもしろ攻略
- ドラえもんの理科おもしろ攻略
- ドラえもんの社会おもしろ攻略
- ドラえもんの小学校の勉強おもしろ攻略
といった多彩なラインナップがありますが、その中でも子どもが「わかりやすかった」、「勉強になった」と言っていた5冊を紹介したいと思います。
第5位: 詩が大すきになる
わが家の子どもは国語が苦手で、特に「詩」に対しての理解力が不足していたので、この「ドラえもんの国語おもしろ攻略 詩が大すきになる」は強制的に読ませました。
結果として、「詩とはどんなものか」を知るきっかけになりました。
ちなみに、令和5年度の三鷹中等教育学校の適正Ⅰでは、この書籍で紹介されていた詩人「まど みちお」さんの作品が実際に出題されていました。
第4位:[新版]すらすら作文が書ける
「ドラえもんの国語おもしろ攻略 [新版]すらすら作文が書ける」は、公立中高一貫校を目指すのであれば、目を通しておいて損はない1冊だと思います。
わが家の子どもは旧版を使って勉強しましたが、現在は岩下修さんが監修された[新版]が出版されており、内容もさらにわかりやすく改良されています。
第3位:「ともなって変わる数」がわかる~関数の基礎~
中学受験を考えているご家庭であれば、読んでおきたいのが「ドラえもんの算数おもしろ攻略 「ともなって変わる数」がわかる~関数の基礎~」です。
関数の基礎をわかりやすく解説した良書であり、算数のつまずきやすい単元をスムーズに理解させてくれます。
わが家の子どもは小学4年生頃から繰り返し読んでいたおかげで、抽象的な概念が増える小学校6年生以降もつまずくことなく、安定して算数の成績を保つことができました。
わが家の子どもは、のび太くんの理解力の高さに怒っていました(笑)
第2位:「政治のしくみがわかる」
「ドラえもんの社会科おもしろ攻略 政治のしくみがわかる」は、小学生にとって実感しにくい選挙や政治の仕組みを、漫画を通してわかりやすく学べる一冊です。
わが家の子どももこの本を読んだことで関心が高まり、池上彰さんのニュース番組を自分から見るようになりました。
特に、小学6年生で習う「公民」の授業に合わせて読むと、理解がいっそう深まると思います。
第1位:「力と電気、音、光がわかる」
『おもしろ攻略 理科シリーズ』はどれもおすすめですが、なかでも 「力と電気、音、光がわかる」 は特に面白かったと子どもが話していました。
一方で、Amazonのレビューには「難しい」といった感想も見られるため、ある程度の基礎力がある子ども向けといえるかもしれません。
それでも、理科のさまざまな現象を漫画でわかりやすく解説してくれる良書であり、理科に苦手意識のある子にも一度は手に取ってほしい一冊だと思います。
「ドラえもん探究ワールド」シリーズについて
なお、似たような参考書として 「ドラえもん探究ワールド」シリーズ もあります。
こちらは各単元ごとに、藤子・F・不二雄さんの単行本から抜粋したエピソードが掲載され、その後に専門的な補足解説が付け加えられる構成になっています。
つまり、漫画自体はドラえもんの単行本と同じなのでご注意ください。


なお、わが家の子どもは補足解説には目を通さず、漫画の部分だけを読んで終わっていました──。
まとめ
勉強は「やらされる苦行」ではなく、「知りたいを叶えるワクワクした遊び」であってほしい──。
小学館の『ドラえもんのおもしろ攻略』シリーズは、その遊びの延長線上で自然に学びが積み重なる理想的な教材(参考書)だと思います。
まずはお子さまの興味に合った1冊から始めてみてください。
気づけば、遊んでいるように笑いながら、知識がしっかり身についているはずです。
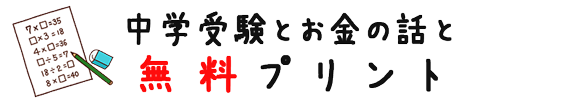
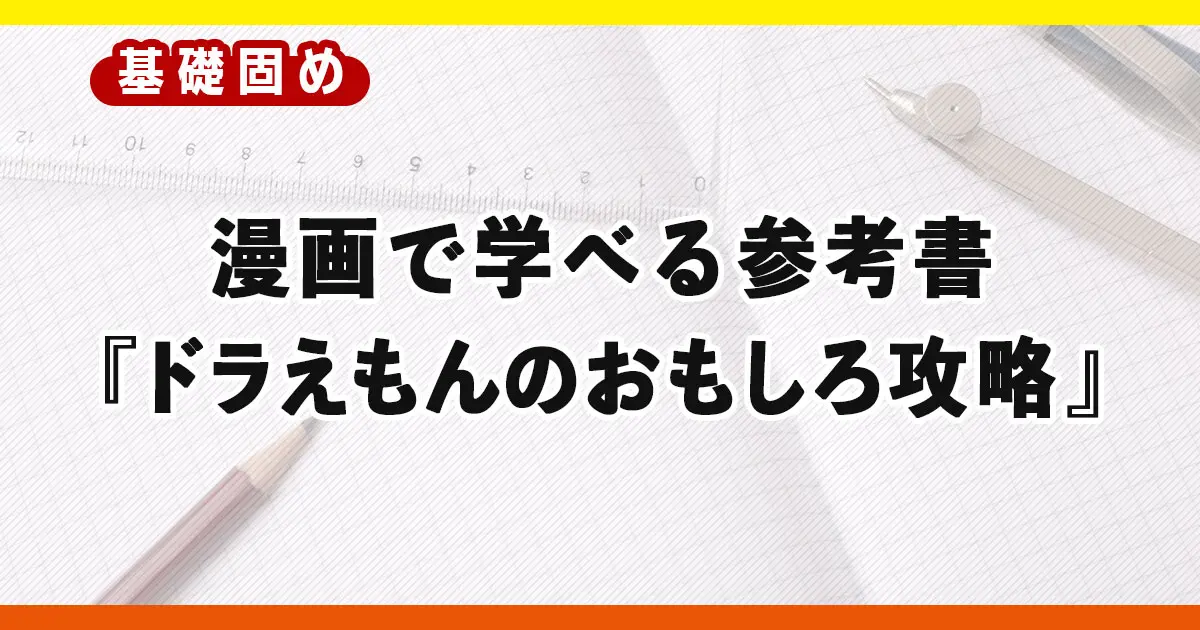






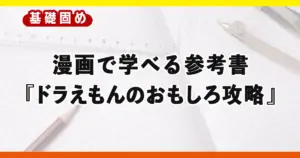
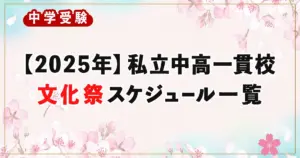
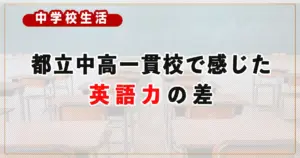
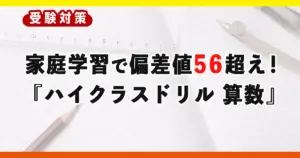
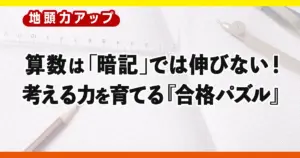
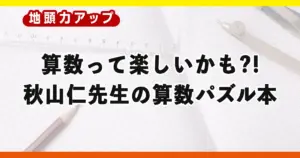
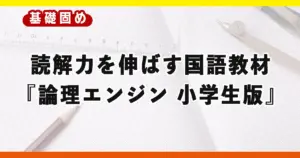
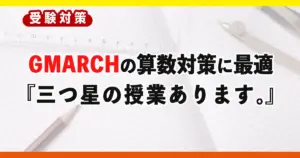
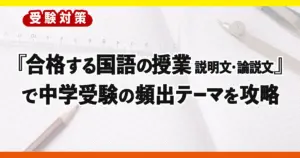
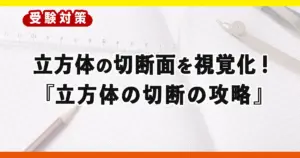
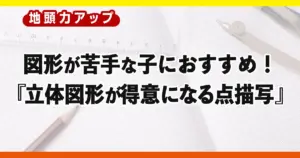
コメント