主に小学3年生になると、社会の授業で覚えることになる「地図記号」。
この地図記号が苦手になってしまうと、小学5、6年生で習う地形図の読み取りでも苦労し、社会科全体が苦手になってしまう…かもしれません。
とはいえ、「ただ覚えるだけ」では、つまらないのが現実です。
そこで今回、主要な地図記号を楽しく学べる4択クイズ形式のWEBアプリを作成しました。
単なる暗記ではなく、それぞれの記号の由来や意味も解説しているので、「どうしてこの形なのか」が理解でき、記憶にも残りやすくなっています。
気軽にチャレンジできるので、ぜひ遊んでみてください。
クイズに挑戦してみる
地図記号4択クイズ|遊び方ガイド
今回、作成した「地図記号4択クイズ」の遊び方についてです。
- 出題形式は 4択問題、制限時間は1問15秒です
- 出題数は ランダムで20問出題されます/全38問中

現在は、「間違えた問題だけを復習する機能」はありませんが、いずれそういった機能も実装していきたいと思います。
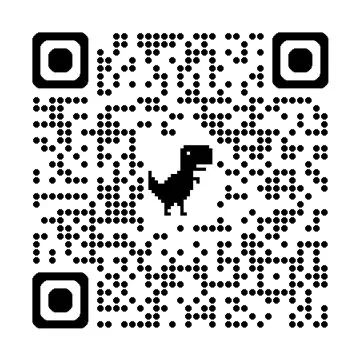
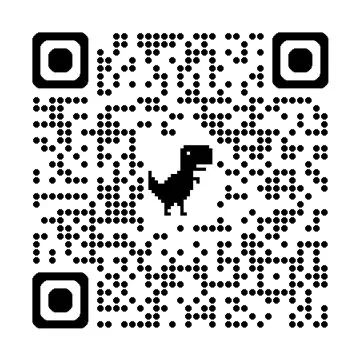
スマホでも遊べるので、スキマ時間にぜひ挑戦してみてください!
どうして地図記号があるの?
この地図記号を決めているのは、日本の地図作りを担当している「国土地理院」という専門機関です。
たとえば、北海道の地図でも沖縄の地図でも、「市役所」や「病院」を表すマークはまったく同じです。
もしも作る人ごとに違う記号を使っていたら──
地図を読むたびに意味を調べ直さないといけませんし、災害時や旅行中など、すぐに情報が必要なときにとても困ってしまいます。
つまり地図記号は、「見てすぐわかる」ための、みんなで使う共通言語のようなものです。
そのおかげで、都市計画や災害対応、教育など、さまざまな分野で地図は大活躍しています。
地図記号って、いつからあるの?
地図記号が日本で本格的に使われ始めたのは、明治時代ごろといわれています。
当時、軍や官庁で地図の整備が進められたことがきっかけで、記号の統一が始まりました。
もちろん、その頃と今とでは使われている記号も違い、時代の変化に合わせて、新しい記号が加わったり、デザインが変わったりしてきました。
たとえば、「老人ホーム」の記号は比較的新しく、高齢化社会を背景に登場したものです。
「形の由来」を知ると覚えやすい!
地図記号には、それぞれ「どうしてその形なのか?」という意味(由来)があります。
たとえば、「交番」のマークは警察官が持つ警棒を交差させた形です。
クイズの解説にもそうした由来を添えているので、是非遊んでみてください。
クイズに挑戦してみる
家族で楽しみながら学べるように「地図記号のかるた」もあるわ。
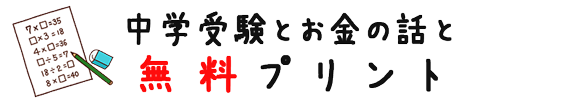
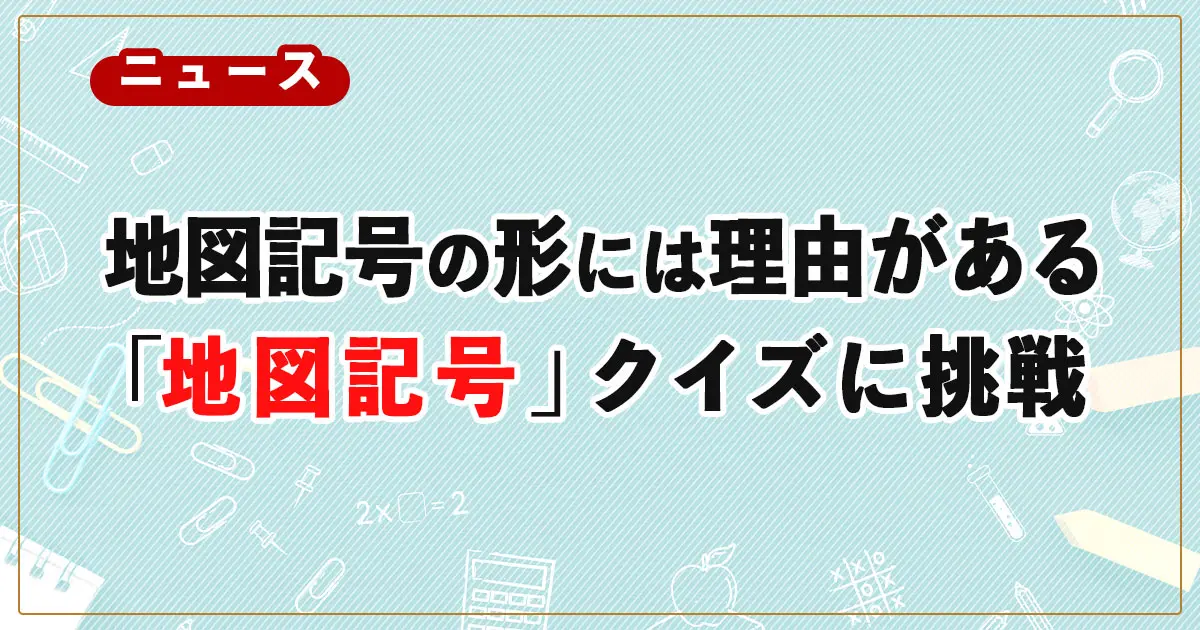

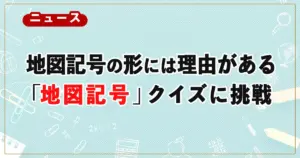
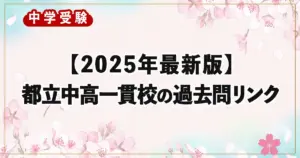
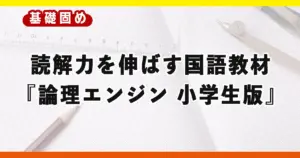
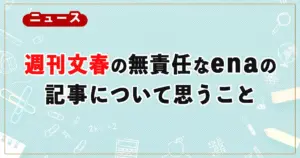
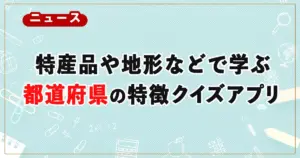
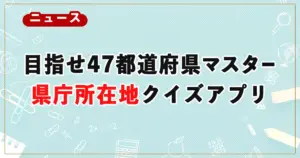
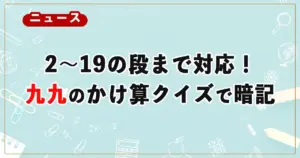
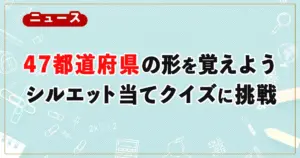
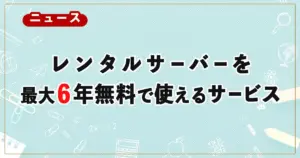
コメント